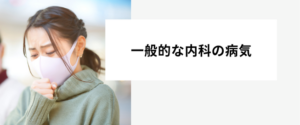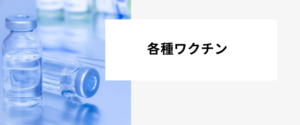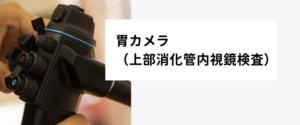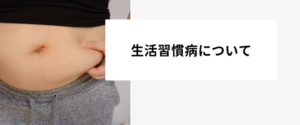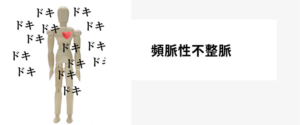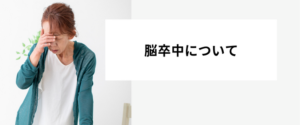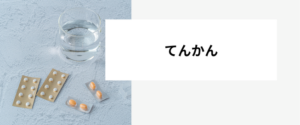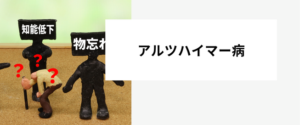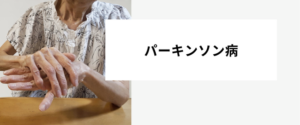髄膜炎とは
髄膜炎は、脳と脊髄を包み込む薄い膜である髄膜に炎症が起こる病気です。原因としては、細菌やウイルス、真菌などが挙げられますが、最も一般的なのは細菌性髄膜炎です。
細菌性髄膜炎は、ウイルス性髄膜炎よりも重症化しやすく、死亡率も高くなります。近年では、ワクチン接種によって患者数は減少傾向にありますが、依然として注意が必要な病気です。
髄膜炎の原因

髄膜炎は、主に細菌、ウイルス、真菌などの病原体によって引き起こされます。それぞれの原因菌によって、症状の重症度や治療法などが異なります。
- 細菌性髄膜炎
肺炎球菌や髄膜炎菌などの細菌が原因で発症します。これらの細菌は、飛沫感染によって人から人へと感染します。重症化すると急性敗血症や敗血症性ショック、脳神経障害などを引き起こす可能性があります。 - ウイルス性髄膜炎
ウイルス性髄膜炎は、エンテロウイルスやヘルペスウイルスなど、様々なウイルスが原因で発症します。ウイルス性髄膜炎は、細菌性髄膜炎に比べて症状が軽症で、自然治癒することも多いです。 - 真菌性髄膜炎
真菌性髄膜炎は、免疫力が低下している人に発症することが多く、重症化する可能性が高いです。原因菌としては、クリプトコッカスやアスペルギルスなどが挙げられます。
髄膜炎の症状

髄膜炎の症状は、原因菌や患者さんの年齢・体質によって異なりますが、主に以下の症状が現れます。
- 発熱:38℃以上の高熱が続くことが多いです。
- 頭痛:頭全体が痛む、ズキズキと痛む、締め付けられるような痛みなどがあります。
- 嘔吐:ひどい吐き気と嘔吐を伴うことがあります。
- 項部硬直(こうぶこうちょく):首が硬くなり、前かがみになるのが困難になります。
- 意識障害:ぼんやりしたり、意識を失ったりすることがあります。
このほかにも、筋肉のこわばりやけいれん、吐き気、光に対する過敏症などの症状が現れることもあります。
髄膜炎は、発症してから短時間で重篤な状態に進行することがあるため、早期発見が重要です。症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
髄膜炎の治療

髄膜炎の治療は、原因菌によって異なります。
細菌性髄膜炎の場合は、早期に適切な抗生物質を投与することが重要です。治療が遅れると、脳神経障害や敗血症性ショック、多臓器不全などを引き起こし、死亡率が上昇する可能性があります。
ウイルス性髄膜炎の場合は、自然治癒するケースがほとんどです。しかし、症状が重い場合は対症療法が行われます。真菌性髄膜炎の場合は、抗真菌薬の投与が必要です。
髄膜炎は、重症化すると、脳神経障害や敗血症性ショック、多臓器不全などを引き起こす可能性があります。これらの合併症を防ぐためには、早期診断と適切な治療が重要です。
髄膜炎の予防

髄膜炎の予防には、予防接種が推奨されています。
日本では、肺炎球菌、髄膜炎菌などに対するワクチンが定期接種または任意接種で受けられます。これらのワクチンは、乳幼児や高齢者など、感染リスクが高い人に接種されることが一般的です。
また、感染拡大を防ぐために、感染症対策としての基本的な手洗いやマスクの着用などの予防対策も重要です。自己防衛だけでなく、周りの人たちへの感染を防ぐためにも、積極的に対策を行いましょう。
まとめ

髄膜炎は、誰でもかかる可能性のある病気です。特に、乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人は感染リスクが高くなります。
もし、ご自身や家族に症状が現れた場合は、迷わず医療機関を受診してください。早期発見と適切な治療が、命を救う可能性を高めます。
また、日頃から予防接種や感染症対策を行うことで、髄膜炎の感染リスクを軽減することができます。一人一人が予防意識を持ち、健康的な生活習慣を送ることで、髄膜炎から身を守りましょう。
Q&A

Q.髄膜炎とは何ですか?
髄膜炎は、脳や脊髄を覆う膜である髄膜が炎症を起こす病気です。細菌やウイルス、真菌などが原因となります。症状には、頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、意識障害、けいれんなどがあります。
Q.髄膜炎の原因は何ですか?
髄膜炎の原因となる細菌やウイルス、真菌などはさまざまです。最も一般的な原因は、肺炎球菌や髄膜炎菌などの細菌です。ウイルスによる髄膜炎もあります。
Q.髄膜炎の症状は何ですか?
髄膜炎の症状には、頭痛、発熱、吐き気、嘔吐、意識障害、けいれんなどがあります。また、光に敏感になる、首が硬くなる、皮膚に紫色の斑点が現れることもあります。
Q.髄膜炎はどのように診断されますか?
髄膜炎の診断には、脳脊髄液検査が必要です。脳脊髄液は、脳や脊髄を覆う髄膜に取り囲まれた液体であり、感染がある場合は異常が見つかります。また、血液検査や画像検査も行われます。
Q.髄膜炎は治療できますか?
はい、髄膜炎は治療できます。治療には、抗生物質や抗ウイルス薬、抗真菌薬などが使用されます。対症療法として、解熱鎮痛薬や抗炎症薬などを使用する場合もあります。
Q.髄膜炎はどのように予防できますか?
髄膜炎を予防するには、ワクチン接種が重要です。肺炎球菌や髄膜炎菌などに対するワクチンがあり、定期的な接種が推奨されています。また、手洗いやうがいなどの衛生的な生活習慣も予防に役立ちます。
Q.髄膜炎にかかるリスクはありますか?
髄膜炎は、免疫力が低下している人や、脳や脊髄に外傷を受けた人、あるいは免疫力が低下している高齢者などのリスクが高いとされています。また、接触感染が原因となることがあるため、集団生活をしている人もリスクがあります。
Q.髄膜炎にかかった場合、どのくらい入院する必要がありますか?
髄膜炎にかかった場合、治療方法や重症度によって異なりますが、通常は数日から数週間の入院が必要となります。病状が軽い場合は、外来治療も可能です。
Q.髄膜炎はどの程度深刻な病気ですか?
髄膜炎は、症状が進行すると脳や脊髄に重大な損傷を与える可能性があるため、深刻な病気です。早期の診断と治療が重要であり、治療が遅れると命にかかわることもあります。
Q.髄膜炎にかかった人が生活する上で気を付けることは何ですか?
髄膜炎にかかった人は、治療を継続することが大切です。また、病気が完治しても、症状が再発することがあるため、定期的な検査を受けることが必要です。また、周囲の人との接触にも注意が必要であり、手洗いやマスク着用などの衛生的な生活習慣を維持することが重要です。
【web予約】
【外来医師担当表】
| 午前 9:00-12:00 ※月曜日のみ10:00-14:00 | 午後 13:00-18:00 ※木曜日のみ13:30-18:00 |
|
|---|---|---|
| 月 | 中村 | |
| 火 | 新福 | 猪瀬 |
| 水 | 猪瀬 | 猪瀬 |
| 木 | 稲垣 | 三宅 |
| 金 | 猪瀬 | 福井 |
| 土 | 猪瀬 |
内科の疾患
当院で掲載している疾患に関する説明は、患者さん並びにご家族の皆様に参考となる情報提供であり、全ての疾患の検査や治療を行えるわけではありません。